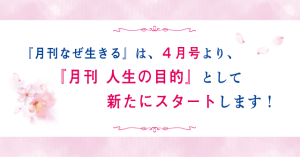木の実の一生
~東北工業大学・アニメ関連授業との共同企画~
小さなトカゲが緑色のシッポをぴん!と立てて、砂ぼこりをたてながら矢のような早さで竹藪の中へ走っていく。
蜜蜂が一匹、ぶんぶん唸りながら花の上を飛び回っている。ここは静かな寺の境内。海に向いたそのあまり広くもない庭の真ん中に空にそびえるようにして大きな樹が立っている。

夏の盛り、この大樹はまるで森のように枝や葉を広げて村人を安心させ、秋にはたくさんの木の実をつけて、鳥たちを喜ばせてきた。
そうやってもう何百年もの間、生きてきた物だから、村人たちはこの大樹を、いつもありがたそうに手を合わせて見上げてきた。
それは、かんかんする夏の日も終わり、次第に深まっていく秋の一日の事だった。
あれほどたくさんついていた木の実も、鳥たちに食べられ、風に落ちたりして、とうとう大樹は実一つになってしまった。どの枝を見ても他には一つの木の実も見当たらない。本当にこの大樹に木の実は一つだけになってしまったのだ。
そのたった一つ残った木の実も、もうすぐ自分も鳥に食べられてしまうのだと思うと心細く、何か淋しい気持ちになって、じっと下の地面を見ていた。そこには、冷たい苔に覆われた黒い石が大樹の陰になって土に埋まっている。木の実は物悲しげにその石を見つめていたが、次第に胸が詰まってきて、思わず大きなため息を一つついた。
すると、ちょうどその時、どこから現れたのか鳥が一羽飛んできて、木の実のなっている枝に、スーッと留まった。
木の実は突然現れた鳥にすっかり驚いて、一瞬、息が詰まりそうになった。それでも恐る恐る鳥を見ると、鳥は赤い羽と赤いくちばしを宝石のように輝かせて、それをまるで木の実に見せびらかすように羽繕いをしながら悠然と留まっている。

木の実はその鳥のあまりの美しさと、その不思議な色に見とれて、あきれたようにしばらくの間ジッと見つめていた。が、ハッ!と気づいて
「あーあ、俺もとうとうこの鳥の腹の中で一生を終えるのか」
とがっかりしてしまった。ところがその時、木の実はなぜか自分でもわからないのだが、思わず、鳥に向かって言った。
「君はいったい、どこから来たの」
と聞いたのだ。
(『月刊なぜ生きる』令和6年2月号より)
続きは本誌をごらんください。

『月刊なぜ生きる』令和6年2月号
価格 600円(税込)