【小説】泣こよかひっ飛べ 第15回 今、ひとたびの旅立ち
(前回までのあらすじ)
桜島を臨む港から、啓一郎を残して武者修行に行く約束をした捨八、圭介、洋介。しかし、残るはずの啓一郎が一人、舟に乗り旅に出た。到着した浜之市から、日向を目指して旅をする最中、踊の村の錦定寺に父からの手紙が届く。支度を整えてから再度旅に出ることを勧める父の手紙を読んだ啓一郎は、一度、家に帰ることを決めたのだった。
◆◇◆
あの日と同じ刻限に、そしてやはり同じ西日の差す寺の縁側に、捨八、洋介、圭介、啓一郎、が一列に並んで座っている。
悠揚と白煙を上げる目の前の桜島も変わることなく、あの日と同じである。違うのはただ、啓一郎の心の内と、他の3人のそれぞれの思いである。

4人はもう長いこと黙ったまま海を向いている。
「あの舟で行ったんだな」と圭介が呟くように言って、沖の方を指差した。
その差す指の先には、やはりあの日と同じ、遠く光る海から宙に浮くように、小さな帆舟が見える。
「そうさ」と洋介が言った。
「でも、せっかく行ったのに、3日で帰ってきちゃうのだものな」と列の端にいる啓一郎をちらっと見て、ちょっと口元に笑みを作って言った。
「道場に行ったのか」と圭介が言った。
「……」啓一郎は黙ったまま首を横に振った。
その答えを意外に思ったのか、圭介は怪訝そうに言った。
「武者修行には出会ったのだろう」
「いえ、会わない」と言って、啓一郎はやはり首を横に振った。
「なんだ。それじゃ武者修行じゃない!」
圭介は自分にも思いもよらない感情が胸中に生じてきて、思わず口に出して言った。
それは啓一郎の旅が自分たちの考える武者修行とは違ったことへの安堵と、年下の啓一郎に先んじられたことを認めたくない思いの現れだった。そして、それを口に出したことへの気まずさを隠すように、また言った。
「ねぇ、捨八さんそうだよね」と捨八に同意を求めた。
しかし、捨八はそれに答えなかった。
「じゃ、何をしてきたのさ」と洋介が言った。
すると、それと同時に、3人の目が一斉に端に座っている啓一郎に注がれた。
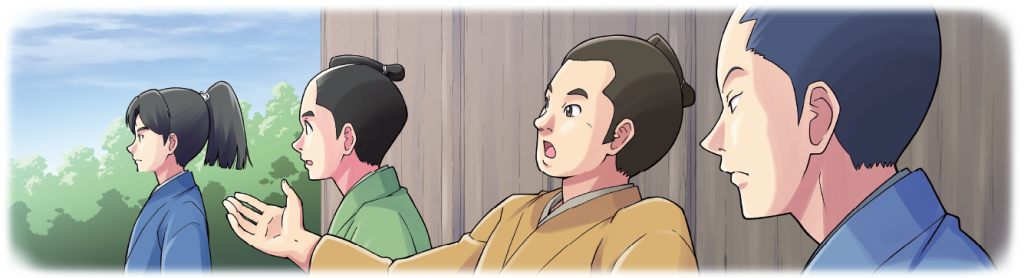
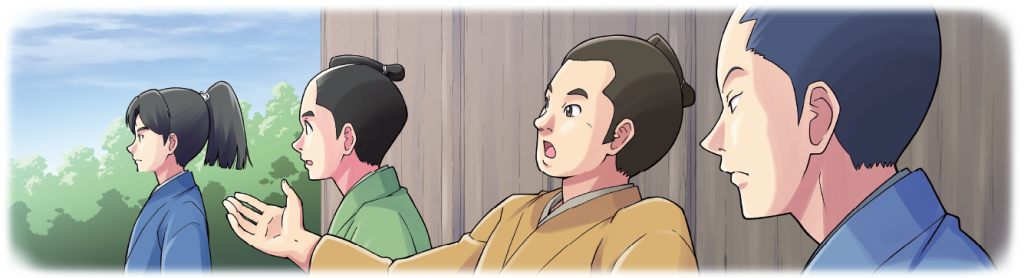


啓一郎は一瞬不意打ちにあった様子でとまどったが、やがて3人の目に答えるように話し始めた。
あの日、朝、1人で3人が来るのを待って、舟頭に促されるままに、覚悟の外に3人が来ないまま舟に乗ったことから始まって、舟中の出来事、浜之市の町の様子、綱ん番のことを話した。
舟中での越中の話は、今でも啓一郎の心の中で気になっていることだった。
霧島では村の役人にご法度破りと怪しまれて、危うく捕らえられそうになったこと。
そして、父の手紙で家に帰ってきたことを、しっかりとした口調で話した。
なぜか日当山に向かう道中で出会った踊り子のことは話せなかった。
ここまでの啓一郎の話を聞き終えた圭介と洋介は真直ぐに啓一郎の顔を見ることが出来ず、西日の眩しさに目を伏せた。
少年たちは無言のまま桜島を見つめていた。
太陽が桜島の肩口から滑り落ちるように沈もうとしている。
やがて少年たちは家族の待つ家路へと就いた。
先を行く圭介と洋介の後を捨八と啓一郎が続いた。
その時、捨八が言った。「また行くのか」とぽつんと呟くように言った。啓一郎はそれには答えなかった。
(『月刊なぜ生きる』令和5年7月号より)
続きは本誌をごらんください。




『月刊なぜ生きる』令和5年7月号
価格 600円(税込)






